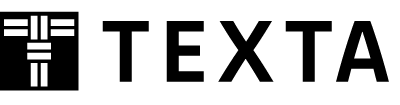「ローカライズ・翻訳」関連コラム
取扱説明書の翻訳
何語から翻訳するか
取扱説明書のようなものの場合、既存の類似のドキュメントがあることも多いので一概にはいえないのですが、まったく新たに色々な言語版のマニュアルを作成するのであれば、日本語から直接いろいろな言語へ翻訳をするよりは、一旦日本語版と同等の内容の英語版を書き起こし、その英語版をハブとして必要な各言語への翻訳を行ったほうがいいでしょう。
英語版をハブにする理由は、日本語からの翻訳者よりは英語からの翻訳者のほうが人数がはるかに多いので、翻訳者も見つけやすく翻訳コストも安くつくという利点があるからです。
英語版(ハブ言語版)を書き起こす理由
単純に日本語版からの翻訳で作るのではなく、英語版(ハブ言語版)を書き起こしたほうがいい理由は、そのままただ翻訳をかけてしまうと、往々にして表現が複雑でくどくなり、ワード数が膨らんで翻訳代がその分上がってしまうからです。
英語版で膨らんだワード数は、その先の各言語への翻訳へもはねかえりますので、できるだけ簡潔な英語版を作るのは、必要な言語数が多ければ多いほど、コストの面で重要になります。
制作に使うアプリ
Tradosに代表されるような翻訳支援アプリとの連携がいいものを使うべきでしょう。翻訳後の手間が大きく変わります。たとえば、必要に応じて印刷用版下にも使える品質のpdfを作るとして、多くの場合はAdobe社のソフトを作成に使うことになりますが、同じAdobeでもIllustratorを使ったときとInDesignを使ったときとではDTPにかかる労力がまったくちがいます。
Illustratorで作成されたファイル上の文言を翻訳する場合は、翻訳対象文言の抽出から原文と翻訳文の入れ替えまで全面的に手作業ということになりますが、InDesignで作成されたファイルであれば、idmlという形式で保存したファイルがそのままTradosでの翻訳原稿になりますし、Tradosを使って翻訳を行えば、原文と翻訳文の入れ替えはほぼ自動で済みます。
扱う言語の特性の把握
また、扱う言語によっては、その言語を扱えるアプリを考慮し、その言語に対応したフォントの追加を考慮する必要も出てくるでしょう。2000年代までに比べると、素の状態でのコンピューターのマルチリンガル環境は格段に整っていますが、それでもヘブライ語やアラビア語のように右から左へ横書きされる言語やベトナム語のようにアルファベットに多くの補助記号がつく言語を適切に扱える環境を構築するにはそれなりの配慮が必要です。
韓国語のように改行位置によって文章の意味が変わる可能性がある言語や、タイ語のように文の区切りが分かりにくい言語などでは、DTP後のネイティブチェックが必須になるかもしれません。