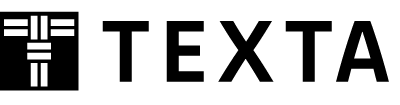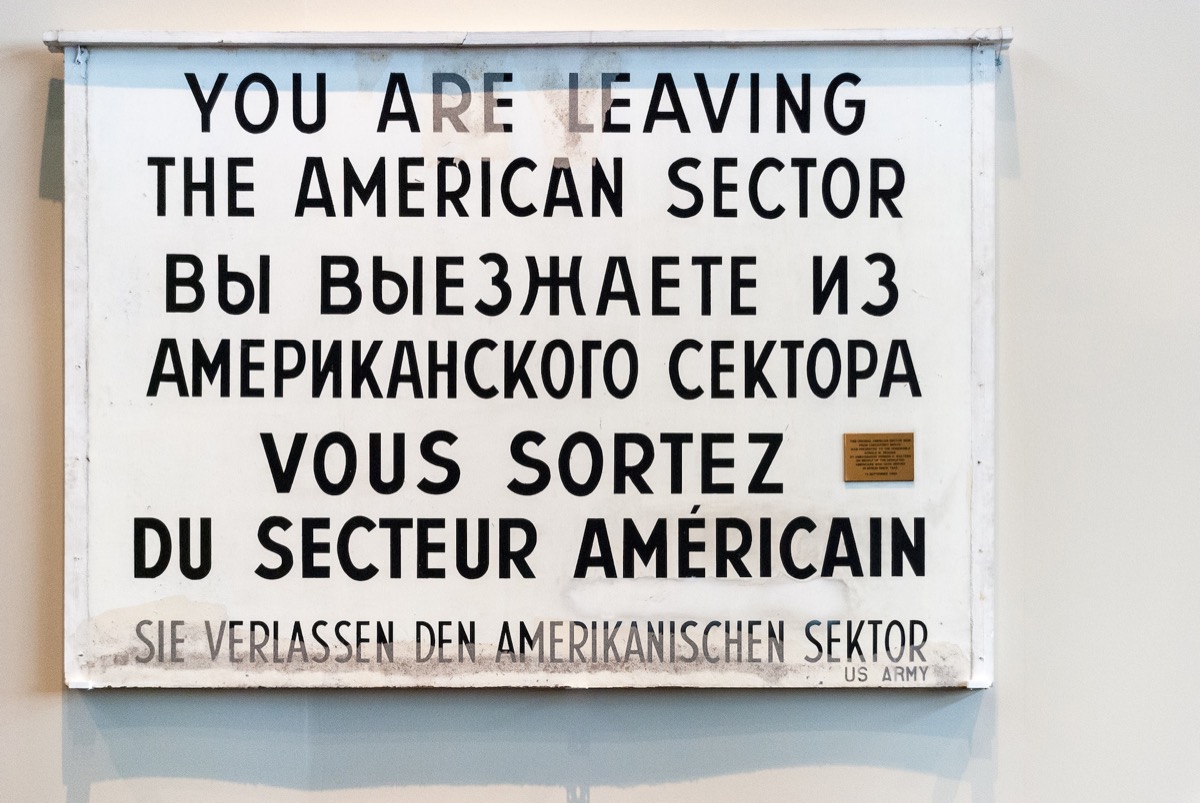
「ローカライズ・翻訳」関連コラム
翻訳支援ソフトや機械翻訳をどう利用するか
2000年代後半以降、SDL Tradosに代表されるような翻訳支援ソフトは、産業翻訳などの分野を中心に完全に定着しています。
また、2000年代末頃から、機械翻訳の性能は飛躍的に上がってきており、使いどころを選べば、実用に耐えるようになっています。
翻訳支援ソフトの利点
Tradosや、それに類する翻訳支援ソフトは、翻訳メモリに蓄積された既存の翻訳を、新たな翻訳の際に類似性の高さに応じて自動的に参照・適用することで、翻訳作業を支援します。
既存の翻訳を的確に流用することによって翻訳量を減らして作業の効率を上げる、という狙いのソフトですので、取扱説明書のような、共通部分や類似部分が多いドキュメントの制作に力を発揮します。同じ文言に対してはできるかぎり同じ翻訳を当てることになりますので、MultiTermなどの用語管理ソフトと併用することにより、用字用語や言い回しなどの統一にも役立ちます。
また、対応するファイル形式のドキュメントであれば、自動的に原文が翻訳文が置き換わった形で翻訳後のファイルを出力できますので、DTPやhtml編集のコストも下がります。
機械翻訳の活用
Google翻訳やDeepLといった機械翻訳サービスは近年飛躍的に翻訳の精度があがり、非常に自然な訳文が得られるようになってきています。けれども一方で、一文がまるごと翻訳されなかったり、否定文が肯定文になっていたりということも頻繁に見受けられますので、翻訳が妥当かどうかの人間によるチェックは現状むしろ必須になっています。
翻訳者の翻訳支援ツールや、上がってきた翻訳のちょっとしたチェックのためのツール、といった用途を超えて機械翻訳を活用しようというときには、訳文の妥当性をチェックする体制をしっかり構築する必要があります。