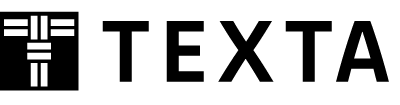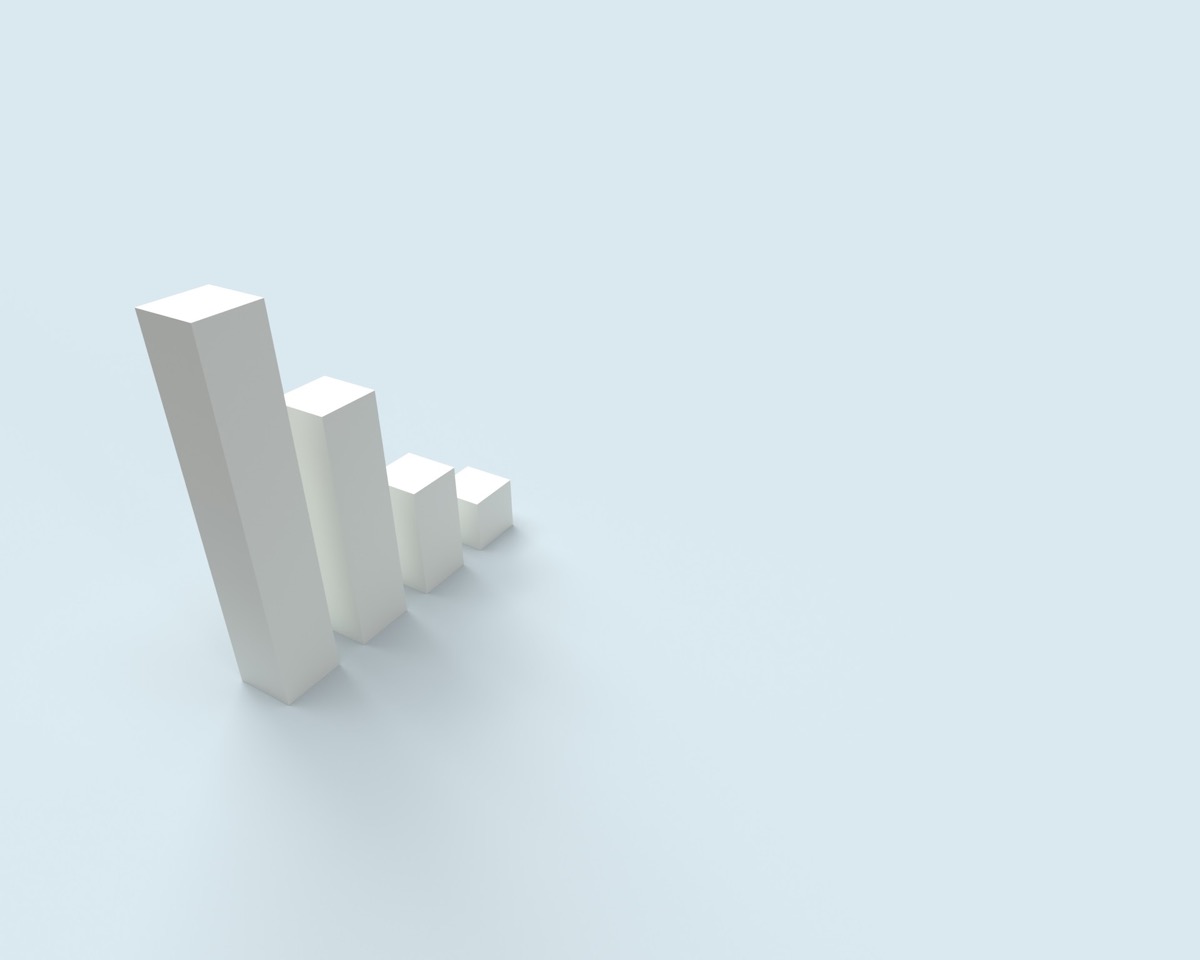
「マニュアル制作」関連コラム
Webマニュアルを解析する
一般的なWebサイトの大きなテーマは「誘導」
企業が自らのWebサイトにEC機能を持たせることが、ごく当たり前のことになりました。それに伴い、Webサイトの性格も単純な「PR」からより動的な「マーケティング・販売」へと戦略的機能性を高めたものに変化しています。ECサイトにおける決済ページなど目標となる地点への強い「誘導」と同等の戦略が、一般的なWebサイトにも色濃く反映されているのです。
製品やサービスを紹介・案内するページから、いかに最終目的ページへと繋げるか、これが大きな課題のひとつになっています。一般的なWeb解析サービスの多くが、サイト上の読み手の振る舞いを詳細に数値化する一方で、「コンバージョン」など「誘導」をより適切に測るための指標に力を入れているのもこうしたニーズに応えるためでしょう。
Webマニュアルのテーマは「問題の解決」
一般的なWebサイトのテーマが「誘導」であるならば、その分析目標は読み手のサイト内における「追跡」になります。広告などの手段で衆目を集める入り口のページから、最終目標ページ(例えば決済ページ)までの訪問者の推移を追いかけることになります。
Webマニュアルでは大きく事情が異なり、読み手のほとんどが「解決すべき問題」を抱え、問題解決につながる情報を欲し探しています。
さらに、読み手の問題がどのページで解決されるかは、抱えた問題に依存するため、Webマニュアルでは「最終目的ページ」を事前に設定することもできません。
Webマニュアルには、独自のWeb解析手法が必要
Webマニュアルでは、一般的Webサイトの解析手法では捉えきれない事象が多数発生します。例えば、ページ滞在時間ひとつをとっても、情報量の割に(記載内容が少ないのに)大変大きくなる場合もあります。それは、そのページを開いたまま読み手が対象となる製品などで問題解決のための実作業を行っているためかもしれません。
また、ごく少ないページ参照だけでサイトから離れてしまう読み手が多数いるような場合、一般的Webサイトでは大問題になるかもしれません。しかし、Webマニュアルでは、それが問題解決を伴っている事象なのであれば、むしろWebマニュアルのコンテンツとしての有用性を示すものと言えます。
このように、独自の解析手法と言っても、独特の方法で指標を収集することにあるのではなく、一般的なWeb解析で収集された各種指標に対する解釈と評価に独自性があるのです。
Webマニュアルは目に見えて進化する
紙冊子を配布する、PDFをWeb上に掲載する、などの方法では、決して手に入らなかった「実際のところ、取扱説明書やマニュアルがどのように利用されているのか」という情報が、Webマニュアルでは比較的容易かつほぼリアルタイムで手に入ります。
こうして得た情報を有効活用することで、Webマニュアルは半ば必然的に進化することになります。これは、紙冊子やPDFでの提供時でも行ってきた改善サイクル、「分析する」「問題箇所を見つける」「改善・修正する」「公開する」をくり返すだけで達成されます。
Webマニュアルと紙冊子のマニュアルとで異なるのは、Webマニュアルではより客観的なデータに基づく分析が可能であり、改善サイクル自体の回転も速いという点と、進化しないWebマニュアルは廃れるのも速い、という点です。