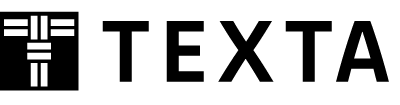「マニュアル制作」関連コラム
紙冊子/PDFからWebマニュアルを作る
PDF/DTPデータからそのままの形でWebマニュアルを作ると
PDFやその元になったDTPデータを直接htmlファイルなどに変換するツールやサービスを利用して、Webページを作成しWebマニュアルとすることは可能です。
しかし、この手法をとった場合、一通り作れたとしてもなお、次の3つの点が問題になります。
- 紙冊子を前提に構成された説明がそのまま違和感なく画面上に移行できるか
- 紙冊子の「ページ順」という秩序によって規定されていた内容がWeb上の検索によってどこからでも読まれる環境に晒されることに耐えうるか
- Webマニュアルのマニュアルとしてのスタンスを維持できるか
紙冊子の「ページ」は、Web上では違和感がある
紙に印刷されたページは、その内容をいささかも変更できないことから、情報を静的に伝えているものと捉えることができます。
一方、Webページでは、読んでいるそばからその表示内容を変更させることが容易にできます。
同じ情報を伝える際でも、静的な手段によるのか、それとも動的な手段によるのかによって、説明の効果は変わります。
動的な説明も可能な環境にあるWebマニュアルが、紙冊子由来だからという理由だけで、静的な説明スタイルを保持し続けることは、わかりやすさ、読みやすさという、極めて基本的な読み手の利益を損ねる可能性もあるのです。
紙冊子の「ページ順」はWebページにそぐわない
紙冊子の説明では、計画的に各種情報が配列されます。ページ順はいわば情報をピラミッドのように積み上げるための秩序として機能しています。
これは、紙冊子のページ数の制約から生まれた工夫、すなわち、徹底して重複を避けてきた結果、ということができます。
そのため、あるページを読み解くために他のページを参照する、ということが紙冊子では当たり前に前提にされています。
一方、Webページには、ページ数や紙面サイズの制約はなく、加えて読み手自身の「検索」によって、ダイレクトに当該ページに到着することが、容易になっています。もし、ここに紙冊子の前提をそのまま持ち込んだ場合、読みたいページに直接辿り着いているのに、そのページを読み解くために、まず他のページを読まなければならないという事態が生じることになりかねません。Webページ上でのこの事態は、とても理不尽であるように感じられることでしょう。
マニュアルとしてのスタンスの維持は難しい
PDFの内容をそのままWeb化してWebマニュアルを作成し、さらに、静的な説明をWebコンテンツに相応しい動的な内容へと変更することを積極的に行った場合、一番問題になるのは、そのマニュアルの一貫性が揺らぐのではないかという点です。
例えば、静的なイラストと文言によって十分に説明されていることを、無理に動画による説明に切り替えても、より良い説明になるとは限りません。
重要なのは、説明対象にとって最適な説明手段を選ぶことであり、その基準を明確にした上で一貫性を保つこと(スタンスの維持)です。
また、ひとつの製品やサービスに対して、紙冊子、動画、Webマニュアル、Webサイト、アプリなどの複数の手段で説明を行う場合、それぞれのアイテムについて十分な役割分担を考え、内容的統一性を保って作成されるべきでしょう。
WebマニュアルにWebコンテンツとしての存在意義を持たせる
PDFからhtmlファイルを作成する方法は、内容を変えずに形式的変換を行うものです。紙冊子の内容は、形式として紙冊子に最適化されて作成されたものであり、Webページとして最適化されたものではありません。
また、紙冊子の内容は、情報供給の手段自体が紙冊子しか存在しないことも前提にされています。しかし今や、情報供給手段は、Webだけに限っても、SNS、動画サイトなど多様な形式を取りうるのです。
紙冊子やPDFが持っている情報と同じ情報を持つWebコンテンツとして、Webマニュアルを作る際に必要なのは、Webコンテンツとしての最適な形式と最適な説明方法を根本的に再構築することに他なりません。
過渡期としての形式的変換
Webマニュアルの最適化のためには、読み手がWeb上でどのように情報を受容しているかを詳細に知る必要があります。
そのために、PDFの内容そのままのWebマニュアルを一定期間掲載し、Web解析データを蓄積する、といういわば実験的な手段としてのWebマニュアルを変換ツールを使用して作成することもあるでしょう。
しかし、これはあくまでも一定期間後に全面改訂をすることが前提であり、事前の要請もなしに読み手に協力いただくことを意味することからも、可能ならば避けるべき方法と思われます。