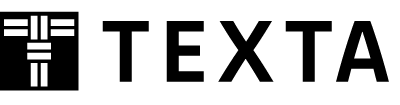「AIサービス」関連コラム
AIサービス対応の背景
AI利用の現状
生成AIが成立した2022年以降、多くの人々がAIの成果を身近に知ることができるようになりました。中でも、対話形式での質問と回答・要約・翻訳・文章作成や、言葉による画像作成など、個人のニーズに応える生成AI利用は、目覚ましい進歩を遂げています。
一方、企業によるAI利用は、機械学習によるモデル構築から学習済みの大規模言語モデルの利用へと裾野が広がってきていることから、より一層進みそうな状況ではあるのですが、個人利用の急拡大のようには進んでいないように思われます。
AI利用の二つの障壁
企業における生成AI利用を考える際、大きく二つの障壁があります。一つは著作権の問題であり、一つはハルシネーション(幻覚)の問題です。
生成AIの基盤となる大規模言語モデル(LLM)は、非常に多くの文章などを学習することで成立していますが、それらの中には著作権が留保された文章も含まれています。直接的ではなくも第三者の著作権が含まれ得る技術を利用し、営利目的でサービスを提供することに対して、企業が躊躇いを持つことは当然と言えるでしょう。また、生成AIは、ときに、根も葉もないことを回答してしまうという事実があります。これもまた、企業が生成AIの本格利用に踏み切れない理由の一つと言って良いでしょう。企業にとって、予測不可能なリスクほど忌避すべきものはありません。
RAGによるブレイクスルー
RAG(検索拡張生成、Retrieval Augmented Generation、ラグ)は、上記の懸念を払拭することができる生成AI利用の一つとして登場しました。その核心は、参照範囲を大きく制限しつつ大規模言語モデル(LLM)の言語能力を十分に活かすこと、にあります。つまり、著作権侵害やハルシネーションの可能性を無視できるレベルで、指定された情報の範囲内についてのみ生成AIを存分に利用できる、ということです。
例えば、自社のWebサイトやPDFについて対話形式で検索する、特定文書を要約・翻訳する、などが、手軽にできるようになります。
人に代わって検索するAI
RAGは、AIによる検索サポートを受けたサービスと位置付けることができます。「Webで検索」といえば、人が自ら入力したキーワードを元に、すべてのWebページを対象とした機械的検索を行うことです。この検索は大変画期的で便利なものですが、一つの大きな弱点を抱えていました。それは、情報量が大きくなればなるほど、検索後、検索結果の長いリストから、本当に知りたい情報を探す必要があったことです。
今後、RAGは、他のAIサービスと組み合わされて、人が本当に知りたいこと・必要なことを人の代わりに検索し一発回答してくれるサービスに進化していくことでしょう。「Webで検索」は面倒だから「AIの検索」が主流になろうとしているのです。
WebサイトがこうしたRAG利用に対応するかどうかは、今後の大きな課題になります。対応を誤れば、AI検索が主流となった世の中で、誰にも読まれない存在しないも同然のサイトになってしまうか、不適切な情報を流し続けることになりかねません。
サービスを利用するのは「人」
私たちは、製品やアプリの取扱説明書やサポートサイトを作成することで、一般向けのユーザーサポートの面で、多くのクライアントを支援してまいりました。そんな中、一般のユーザーを取り巻く環境はこれまでにない転換期を迎えているように思います。ユーザーが使用するPC・スマートフォンなどのデバイスは、次々とAI機能が強化され、AI利用はユーザーの日常に広く深く静かに浸透し始めています。
従来型の取扱説明やWebサイトのサポートページには、長年に渡って蓄積された独自の工夫や知見が豊富に含まれていると思います。AI利用が進む中、もしそうした豊かな情報源が、AI利用から丸ごとこぼれ落ちてしまうようなことがあれば、製品・アプリ・サービスを利用するユーザーにとっても、提供する側の企業にとっても、大変不都合であり不便なことになりかねません。
AI最適化には形式面以外の要素もある
Webサイトのサポートページや取扱説明書などの従来型のユーザーサポートに対してRAGに代表されるAI利用を導入する際に、Webページ、PDF、文書ファイルなどのデータ形式面の課題がまず目につきます。導入前に、AI最適化されているケースはほとんどないでしょうから、まずAI利用にふさわしい形に変換する作業が必要です。
一方で、そうした形式面の課題さえクリアできればAI導入が果たせたと考えるのはいささか早計であると言わざるを得ません。
ユーザーが、ユーザーサポートに求めることは実に多種多様であり、AI導入後であっても、それらの要望にスムースに対応できるかどうかが引き続き評価の対象となります。その意味では、AI導入の有無は、ユーザーサポートの成否を決める決定的要素にはなり得ません。
企業がどのようなサービスをユーザーに提供できるのか・すべきなのか、ユーザーにとってどのようなサービスが必要なのか・好ましいのか、こうした観点からの判断が常に必要になります。