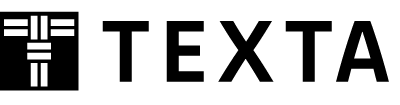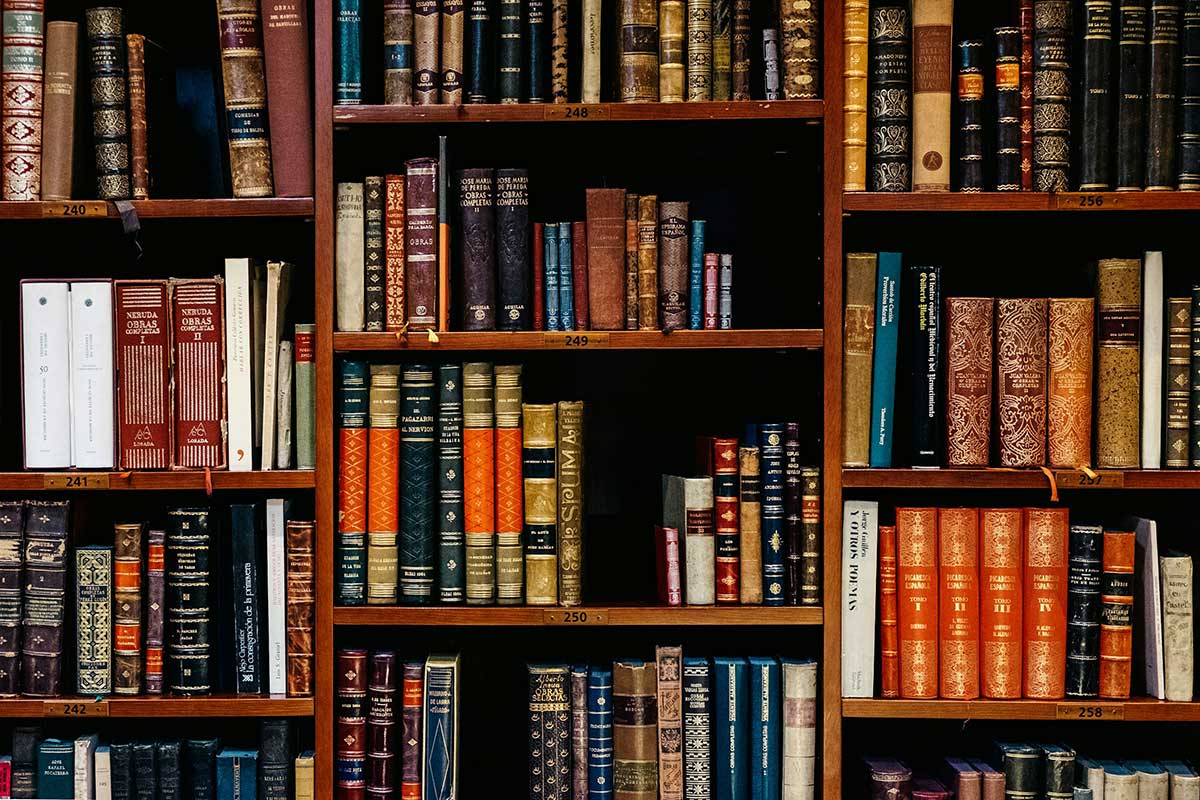
「AIサービス」関連コラム
サポートサービスへのRAG導入
RAGの位置付け
RAG導入のメリットについて、サポートサービスの利用者側と提供者側の二つの視点で捉えてみます。
●サポートサービスの利用者
自分に必要な情報を探す手間が大幅に削減される新しい検索手段:
個別の製品・アプリ・サービスなどの取扱説明には、使い始めから使いこなしまで、広範囲にわたる情報が記載されています。さらに、こうした情報は下位のカテゴリーによって幾度も分類され細かくなっていきます。
こうした細分化は利用者への配慮から行われるのですが、細分化によって、利用者が必要な情報を探しにくくなるということも起こり得ます。
RAGの導入によって、利用者は、対象となる情報群の細分化の文脈とは無関係に、必要な情報にたどり着けるようになることが期待されます。
●サポートサービスの提供者
多種多様な情報を分割することなく体系的かつ一元的に提供する機会:
製品・アプリ・サービスなどを提供する企業側は、ユーザーレベルに応じた提供情報を質と量の双方の観点から整理分類する必要があります。さらに、紙冊子、PDF、Webページ、などのメディアから、目的別に情報提供の方法自体を選定する必要もあります。特に、Webページでの情報提供は、多くの人がスマートフォンを利用する現在最有力の方法と言えます。しかし、Webページ上の情報は、提供側の事前の意図とは別に、内外からの検索で、どこからでもアクセス可能であり、利用者が開いたページに望む情報があるかどうかについて、明確な裏付けもありません。
RAGの導入によって、利用者が、必要とする情報により容易にたどり着けるならば、事前の情報の細分化と整理の作業は、大幅に削減できることが期待されます。
RAG導入のサポート
Webページ、PDF、ファイルを対象に、作成前、作成中、作成後を問わず、説明的な文書に対するRAG導入のサポートを行います。
特に、取扱説明書やマニュアル/ヘルプ
商品やサービスに付随する取扱説明書/マニュアル/ヘルプなどに代表される、知識と手順から構成されるドキュメントについて、ユーザーサポートの視点から、より効果的なRAG利用をご提案いたします。
ドキュメントを精査
RAG利用について、ドキュメントの形式的変換やAIシステム側の調整だけでなく、ドキュメントの質自体を精査することができます。
回答の質にこだわる
RAGによって生成された回答について、その正確性だけでなく、使い手にとっての有益性・実効性に着目し、サポートとしての価値向上に努めます。
ドキュメントの編集・統合
文書作成経験から得た知見をもとに、ドキュメント上の課題を見つけるとともに、修正、削除、追加などの編集を行います。
また、情報内容が同じでありながら、ユーザーレベルに対応するために分散してしまったドキュメントなどについて、RAG利用を前提とした統合を行います。
RAG利用前のご提案
既存の文書について、どのようなRAG利用が可能なのかを提案いたします。
RAG導入の目的
RAG導入の際に重要なことは、RAG利用によって可能になることが、使い手であるユーザーに対してどのような利益をもたらすのかを明確に設定すること、すなわちユーザーサポートの目的を明らかにすることです。
プロトタイプ作成
RAG導入をご検討中の場合には、まずは比較的小さなプロトタイプを短期間で作成し、一定期間の仮運用を行いながら、導入目的や具体的なゴールをより明確にすることができます。
RAG利用中のご提案
どのようなAIシステムであっても、<問に対する答>の質が向上しなくては、満足できるものではありません。
独自のテストおよび評価
ユーザーサポートの目的を念頭に、運用中または仮運用中のRAGに対する独自のテストおよび評価をご提供いたします。
ドキュメントとシステムの見定め
生成される回答の質の評価が、ドキュメントの形式的変換やAIシステムの調整だけで解決できるものなのかどうかを見定めます。
使い手の知識に応じる
一般的な商品やサービスに付随するドキュメントには、初めての購入者から商品知識が豊富なベテランユーザーまで、実に多様なユーザーが想定されます。
知識量に応じた多様なドキュメント
ユーザーに期待できる知識量に応じた多様なドキュメントの内容とその提供意図を合わせて吟味することで、効率と実効性を兼ね備えたサポート構築をご助力いたします。
ドキュメント自体を再構成
使い手の知識量に基づいたドキュメント自体を再構成・統合することで、オリジナルドキュメントを超えるより効果的なRAG利用の可能性を追求するなど、使い手の利益を第一に考えたご提案を行います。
品質維持と向上
実運用開始後は、運用実態を評価した上で、課題を発見し、さらなる品質向上に寄与することができます。
使い手の動向
独自のテストおよび評価に加え、Webページが対象であれば、Web解析などを駆使して、使い手の最新の動向をレポートいたします。
ニーズの先取り
実運用後の<問>と<問に対する答>の分析を通じて、使い手のニーズを把握し、場合によってはそれを先取りすることもご提案いたします。
翻訳への対応
RAG利用では、想定された言語以外の利用も可能です。日本語と英語以外の特に重要な言語については、自動で生成される翻訳について、日本語や英語と同等の品質評価を行います。